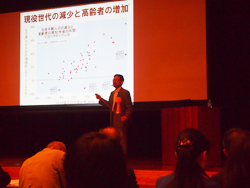 「現役世代人口減は地域経済自立のチャンスでもある」と述べる藻谷主席研究員
「現役世代人口減は地域経済自立のチャンスでもある」と述べる藻谷主席研究員
県内のJA、JA長野中央会など各会、県生協連、県漁連、県森連、県労金、労協ながので構成する長野県協同組
合連絡会は、長野市のJA長野県ビル・アクティーホールで「協同組合シンポジウム」を開いた。構成団体の組
合員・役職員と一般聴講者合わせて220人が聴講した。
同シンポジウムは、協同による心豊かな暮らしやすい長野県づくりに向けた学習活動の一環。今回は里山を見
詰め直し、地域経済の自立を促す「里山資本主義」の考え方を学んだ。
基調講演を行った(株)日本総合研究所調査部の藻谷浩介主席研究員は「日本では現役世代が非常な勢いで減
っている。価値観を改め、食料や自然エネルギーの自給率を高めて長持ちする社会を構築する必要がある」と
指摘した。
藻谷氏はその上で「耕作放棄地、立木、はね出しの農産品など従来価値が認められなかったものでも、資源と
して生かせば、食料+エネルギーの自給率が高まる」と地域内循環経済の重要性を述べる一方、「里山資本主
義での成功事例があっても、横の連絡がなさ過ぎる」と、外への発信が今後の課題だとした。
続いて民間非営利団体(NPO)阿智村地域おこし協力隊の大藪政隆氏が「阿智村における里山資本主義モデル
の取り組み」について事例報告を行った。
大藪氏は、2003年の智里西製材クラブ設立による地域協同型の自伐林業について説明。「凍結原因となる木の
伐採や、委託を受けての間伐、不要木伐採で出る木は、当初ほとんどが丸太でしか販売できなかったが、製材
と木工製品作りを組み合わせることで収益アップが図れるようになった」と話した。
大藪氏はさらに「小さな地域需要を着実に起こすことで地元に木を流通させる仕組みづくりが進んでいる。将
来は自然エネルギーによるエネルギー自給率向上にも結び付けたい」と述べた。
最後に「協同活動や協同組合間協同などの取り組みをさらに進め、社会の『持続可能性』向上に貢献するとと
もに、その取り組みを発信し、協同組合運動への県民・国民の理解促進と共感づくりを進める」とした「第92
回国際協同組合デー・第44回長野県協同組合連絡会宣言」を全会一致で確認した。


